目次
建設業の見積期間、2025年の改正でどう変わるかご存知ですか?
「見積期間が短すぎて、本当に間に合うか不安…」「発注者と受注者、どちらがどんな責任を負うの?」と疑問に思っているのではないでしょうか。
新法では材料費等記載見積書の提出が一層重視され、努力義務や例外規定も明確化。
見積期間のカウント方法も「土日祝日を除外」「やむを得ない事情の具体的事例」など、実務で迷いやすいポイントが細かく整理されています。
本記事では、建設業の見積期間について2025年改正のポイントを交えて解説します。
最短で最新情報をキャッチして、「予期せぬトラブル」や「無駄なコスト」を防ぎたい方は、ぜひ本文もチェックしてください。
建設業法による見積期間とは

建設工事に携わる請負業者が、施工を任せる予定の下請業者へ見積を依頼する際、作成・交付するために設ける期間を「見積期間」と呼びます。
建設業法第20条第4項では、建設工事を発注する上でのルールについて以下のような法律を設けています。
- できる限り具体的な内容を提示すること
- 法律で定める期間を設けること
参考:e-Gov法令検索|建設業法
見積期間が定められている理由
見積に対して必要な期間を法律で定めた理由は、下請となる業者の保護と取引の適正化を図るためです。
見積を行う期間に対して法律がないと、下請業者は契約内容を十分に吟味・把握した上で検討できない恐れがあるほか、元請業者に言われるがまま契約を進めなければならなくなるなどのさまざまなリスクがあります。
国はこのようなリスクを考慮し、元請業者・下請業者双方が納得できる契約を結べるよう一定の期間を定めているのです。
- 大手求人サイトで全国トップクラスに輝いたアドバイザーが在籍
- 年収1000万円以上になった方も
- 年収350万円以上の大幅UP事例もあり
- 業界特化で「分かっている」提案。企業知識が段違い
- 休日や夜間でも専属アドバイザーが対応
建設業法における見積期間:最新改正・法規・実務の全てを網羅
2025年改正建設業法の主要ポイント

近年の建設業法改正では、見積期間の取り扱いや見積書の内容記載に関する規定が強化されています。
特に発注者が見積依頼を行う際には、契約内容提示から適切な見積期間を設ける必要があり、金額ごとに最低日数が明示されています。
発注者が提示すべき見積期間の基準は以下の通り。
| 工事の予定価格 | 見積期間の下限(原則) | 例外時の最低日数 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 1日以上 | |
| 500~5,000万円未満の工事 | 10日以上 | やむを得ない事情5日以上 |
| 5,000万円以上の工事 | 15日以上 |
- やむを得ない事情がある場合、国土交通省通知に基づき5日まで短縮できるが、発注者の記録保存・理由説明責任が生じます。
- 見積期間は「提示日から契約締結日まで」を1日単位で数えます。
- 見積期間は税込金額で判定されます。
この下限を守らずに早期契約を迫ることは法律違反となり、罰則の対象となります。
工事予定価格や工事内容などあらゆる状況を十分に考え、双方にとって納得できる見積書に仕上がるよう十分な見積期間を設けることが望ましいと言えるでしょう。
見積期間の日数の数え方
見積期間の日数には見積依頼日と見積提出日を含んでいません。
仮に、100万円の工事を6月1日に依頼する場合は、翌日の6月2日を「1日目」と数え、見積依頼日に該当します。
下請業者が見積を提出する日はさらに翌日になるので「6月3日が見積提出日」になります。
土日などの休日
見積期間において多くの現場担当者が悩むのが「土日祝日のカウント方法」です。
建設業法や国土交通省ガイドラインには、「土日祝日を除外するか」について具体的な記載はありません。
しかし一般的には、発注者と受注者双方の実務負担を考慮し、営業日(平日)でカウントするケースが多いです。
- 原則:土日祝日を含めて暦日で計算するのが基本
- 実務運用:業者との協議や発注内容により平日だけをカウントする配慮がなされる場合が多い
- 例外:協議の上で見積期間延長が可能
トラブル防止のため、契約書や見積依頼書にカウント方法を明記しておくのが推奨されます。
疑義があれば発注者が国土交通省や建設業団体などへ事前確認を行うと安心です。
見積期間短縮の条件・「やむを得ない事情」とは
建設業法で定められる見積期間は、発注者が下請け企業に見積を求める際、公平な契約機会を守るために定められています。
しかし、どうしても見積期間を短縮しなければならない場面には「やむを得ない事情」という例外が認められています。
「やむを得ない事情」の定義と具体事例
具体的な「やむを得ない事情」は法律上で厳密に定義されていませんが、実際には以下のようなケースが代表的です。
- 災害や事故による緊急工事
- 社会インフラの突発的な復旧要請
- 発注者が国や自治体の場合で、予算繰りや国土交通省など行政手続きの都合があるとき
これに該当するかは各案件ごとに総合的な判断が必要です。
そのため、工事内容など客観的な事情を明示し、短縮理由をきちんと記録しておくのが重要です。
見積期間短縮時のリスクと法的責任
見積期間を「やむを得ない事情」で短縮する場合、発注者は慎重な対応が求められます。
不当に短縮された場合や、単なる発注者都合では建設業法違反となり、国土交通省など行政指導や厳格な罰則の対象になる恐れがあります。
下記はリスクや主な注意点です。
- 不当な見積期間短縮は、下請法や建設業法上の違反リスクがあります。
- 十分な見積判断時間を与えない場合、契約の無効や損害賠償の問題に発展する場合があります。
- 見積提出日の設定や土日祝日の取扱いも明記し、誤解が出ないよう管理することが大切です。
発注者は文書やメールなどで見積依頼日と提出期限を明確化し、下請事業者が問題を感じた場合には国土交通省や監督行政へ相談が可能です。
要求された見積期間が著しく短い場合、対応や記録を残しておくことで後のトラブル回避につなげることができます。
上記を十分踏まえて、発注者も下請も適正な工事契約プロセスを厳守することが信頼構築への第一歩と言えるでしょう。
公共工事と民間工事における見積期間の違い
公共工事と民間工事で適用基準や運用実態に若干の違いがあります。
公共工事
- 法に厳密な基準が適用され、国土交通省・発注機関の監査も強化されています。
- 見積期間に土日・祝日を含めるかは、公告文等で明記、または慣例で除外するケースが多いです。
- 発注者は下請法や随意契約ガイドラインも遵守が必須となっています。
民間工事
- 基本的には建設業法の基準が適用されますが、発注者独自の規定が加わる場合があります。
- 土日祝日の取扱いも現場判断に委ねられるケースが多く、休日分の加味が求められる場合もあります。
- 発注者との事前調整や書面での交渉をする事が求められます。
2025年改正での追加・変更点の補足
2025年の建設業法改正では、見積期間に関する運用の明確化が進みました。
やむを得ない事情による短縮ケースをガイドライン・通達でより具体的に例示し、ルール明文化がなされています。
また、下請業者への見積依頼時に「税込金額の明示」や提出期間の根拠明記が義務になります。
主な追加・変更点
- 発注者は下請に見積依頼する際、税込価格・見積提出期日・短縮理由(必要な場合)を全て文書で伝達
- やむを得ない事情が発生した時、内容ごとに個別判断・記録を義務化
- 国土交通省によるガイドラインで「休日の取扱」や「具体的短縮事例」を最新更新
今後は、すべての事業者がガイドラインを参照しながら、現場と法令とのズレが生じないよう慎重に運用していくことが求められます。
こうした改正点を現場で即座に反映できるかどうかが、発注・受注側双方にとって信頼とリスクマネジメントの鍵となります。
建設業法が定める見積提出時において明示が求められる項目

元請業者が下請業者に見積を依頼するときは以下の点を必ず説明しましょう。
- どの範囲の見積を行う必要があるのか
- 条件や具体的な工事内容の明記
下請業者への説明や下請業者側が見積を行うときは下表を参考にしてください。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 工事名称 | 公共工事の場合は元請業者から指定された名称を記載する |
| 施工場所 | 施工場所を記載 固有名詞や住所で記載するのが一般的 |
| 設計図等の関連書類 | 必要な数量が拾えるよう、図面等の必要書類を貼付する |
| 工事工程や全体工程 | 発注工事の工程、全体の工程などを記載 |
| 見積の条件 | 工事に含める範囲や含めない範囲を明確に定め、提示する |
| 施工環境、制約 | 埋設物の有無・地盤の強度に関する事柄・近隣住民に家族層が多いなど、周辺環境に必要な配慮事項を記載 |
| 材料費、労働災害防止対策など | 下請業者・元請業者で費用をどのように分担するかを記載 |
見積の内訳も明示する必要がある
下請業者が見積書を完成させる際は、提出する前に費用の内訳が明記されているかを確認しましょう。
具体的には、工事種別ごとの材料費や労務費、その他に必要とする経費等です。
これらの経費に対して数量または単位を記載し、元請業者が見積の内容を一目で把握できるよう明記する必要があります。
建設業界では「工事代金一式」など簡略的な記載が用いられることがありますが、この表記は認められていないので注意が必要です。
また内訳には法定福利費を記載することも必須となっています。
法定福利費とは、企業が義務として負担しなければならない費用のことです。
例えば以下のようなものが該当します。
- 健康保険
- 社会保険
- 年金保険
- 雇用保険
必要となり得る予算を確保した上で現場従事者の保険に加入するため、法定福利費も内訳に記載するよう注意しましょう。
建設業法違反に抵触する可能性のある行為
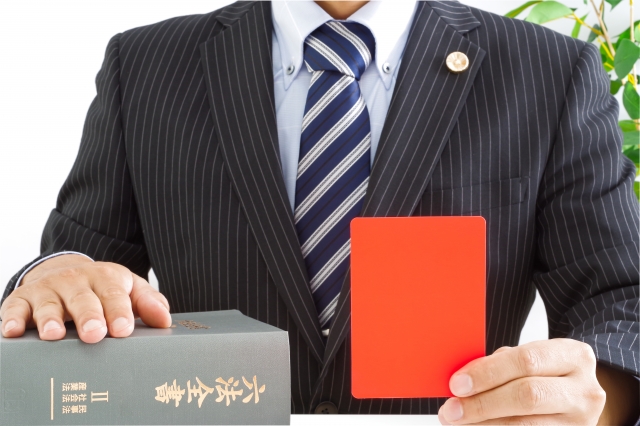
建設業法で定められている見積期間ですが、違反とみなされる可能性のある行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
建設業法令遵守ガイドライン(第9版)では、以下のような行為を建設業法違反に抵触する可能性のある行為としています。
- 元請業者が工事内容や指示をあいまいなまま見積を行わせること
- 元請業者の都合で下請業者の見積を早めること
- 下請業者から工事に関する質問を受けたにもかかわらずきちんと解答しなかったりあいまいにすること
これらに該当するとみなされた場合、元請業者は建設業法違反に問われる恐れがあります。
例えば以下のような場合は建設業法違反に該当します。
発注予定金額が2,000万円の下請け契約を結ぶ際に、見積について早く把握したく3日に設定して下請け業者に見積もりを行わせた
参考:国土交通省不動産・建設経済局建設業課|建設業法令遵守ガイドライン(第9版)
\ 誰かに聞いてほしい悩みはありませんか/
発注者・受注者それぞれの見積プロセスと業務フロー
建設業法に基づく見積期間は、発注者・受注者双方にとって非常に重要です。
発注者は、下請業者が適正な見積書を作成できるよう十分な期間を提示する責任があります。
一方、受注者は、提示された契約条件や仕様を正確に読み取り、法定の見積期間内に精度の高い見積書を作成することが求められます。
下記のようにそれぞれのフローを整理すると業務がスムーズになります。
| 発注者の業務フロー | 受注者の業務フロー |
|---|---|
| 1. 契約内容・仕様の精査 | 1. 依頼内容・図面の確認 |
| 2. 見積依頼書・注文書の作成 | 2. 契約条件の精査 |
| 3. 必要な見積期間の設定 | 3. 法定見積期間の妥当性確認 |
| 4. 下請業者・協力会社へ依頼 | 4. 積算および原価計算 |
| 5. 法定期間遵守の管理 | 5. 質問事項があれば問い合わせ |
| 6. 見積書受領・内容確認 | 6. 見積書の提出 |
契約内容の事前提示と見積依頼時のチェックリスト
見積依頼時には、依頼内容に漏れや曖昧な点がないよう、契約内容を事前に明確に提示することが重要です。
迅速かつ適正な見積作成を実現するためには、下記のチェックリストに沿った準備が有効です。
- 契約書・注文書・仕様書の事前提示
- 設計図書・施工条件の詳細説明
- 適正な見積期間の設定(建設業法の基準遵守)
- 土日祝日や連休を考慮した見積期間の計算
- 見積内容や数量の相違が発生しやすい箇所の明示
- 国土交通省等のガイドラインへの遵守確認
- 税込見積・法定福利費など諸経費記載の指示
これらにより、誤解やトラブルを未然に防ぎ、発注者・受注者双方の業務効率化とコンプライアンス強化が図れます。
下請法・注文書との関連性と実務対応
見積期間の設定は、下請法や注文書の作成とも密接に関わります。
建設業法だけでなく下請法の観点でも、見積期間を不当に短縮した場合には法的リスクが生じます。
また、注文書や契約書には、見積内容や期間の根拠、やむを得ない事情による短縮の有無を必ず明記することが求められます。
- 下請法による支払い・締結ルールの確認
- 注文書・契約書作成時のチェックポイントの徹底
- やむを得ない場合の見積期間短縮理由の文書化
- 見積書提出期限を逸脱した場合の対応フローの整備
- 発注者は適正なリードタイムを確保し信頼関係を構築
これら実務対応を徹底することで、発注者・受注者ともに不利益やトラブルを回避し、持続的な事業パートナーシップを築くことが可能になります。
見積を作成するときは見積期間のルールに注意しよう
元請業者および下請業者は、見積期間に則った範囲で見積書を受納・発行する必要があります。
下請業者に対して見積書の発行をむやみに急かすなどの行為は、建設業法違反とみなされる恐れがあります。
建設業界に携わる人や個人事業主として活躍する人は、この機会に見積期間や建設業法に理解を深めてみてはいかがでしょうか。
有料職業紹介(許可番号:13-ユ-316606)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社ゼネラルリンクキャリアが運営しています。








