目次
建設業界で働く場合、1級土木施工管理技士の資格はぜひ取得したいところです。
しかし、資格取得を考える方にとって、試験の合格率や難易度が気になることでしょう。
本記事では、1級土木施工管理技士の合格率から試験の難易度について考察し、受検資格や必要な実務経験なども解説します。
記事を参考にすれば、あなたの実力で1級土木施工管理技士に合格できるかの判断基準になります。
ぜひ、本記事に目を通し、試験を受けるかどうか見極めてください。
1級土木施工管理技士の合格率を徹底分析

1級土木施工管理技士は、工事に必要な主任技術者や監理技術者に必須の国家資格です。
仕事内容の幅が広がりキャリアアップも目指せる資格のため、人気の高い資格です。
ここでは、試験に関するさまざまなデータを紐とき、1級土木施工管理技士がどれくらいの難易度なのかを明らかにします。
過去の合格率データ
1級土木施工管理技士試験の過去5年間における合格率は、1次検定が55.9%、2次検定が34.9%でした。
令和5年度の合格率は第1次検定が49.5%、第2次検定が33.2%となり、過去5年間の合格率を下回っています。
| 第1次検定(令和2年度までは学科試験) | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和5年度 | 32,931人 | 16,311人 | 49.5% |
| 令和4年度 | 38,672人 | 21,097人 | 54.6% |
| 令和3年度 | 37,726人 | 22,851人 | 60.6% |
| 令和2年度 | 29,745人 | 17,885人 | 60.1% |
| 令和元年度 | 33,036人 | 18,076人 | 54.7% |
| 第2次検定(令和2年度までは実地試験) | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 令和5年度 | 27,304人 | 9,060人 | 33.2% |
| 令和4年度 | 24,462人 | 7,032人 | 28.7% |
| 令和3年度 | 26,558人 | 9,732人 | 36.6% |
| 令和2年度 | 24,204人 | 7,499人 | 31.0% |
| 令和元年度 | 24,688人 | 11,190人 | 45.3% |
参考:日本建設情報センター
合格率からみる試験の難易度
過去10年間の第1次検定(学科)の合格率は55〜60%程度であり、難易度は高くありません。
一方、第2次検定(実地)では2022年度が28.7%、2021年度が36.6%となっています。
試験内容自体の難易度は、一般的に高くはないと言われています。
しかし、1次・2次の両方を併せたトータルでみると、気軽に取れる資格とはいえません。
とくに、高校や専門学校などで特定の学科を履修していない場合、より多くの勉強時間が必要となります。
また、土木施工管理技士の受検には実務経験も求められるため、受検する年齢に大きな影響を与えます。
学歴によっては10年以上の実地経験が無くてはならず、試験の難易度以上に実地経験の積み上げに苦労する方もいるでしょう。
他の建設関連資格との合格率比較
ここでは建設業に関連するほかの資格と、1級土木施工管理技士試験の合格率を比較してみます。
| 資格 | 直近の合格率 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 1次検定:55.9% 2次検定:34.9% |
| 1級建設機械施工技士 | 30.1% |
| 測量士 | 10.3% |
1級建設機械施工技士と比較
1級土木施工管理技士の1次検定の合格率は50%ほどで、第2次検定は30%ほどとなっています。一方、1級建設機械施工技師は30%ほどとなっており、合格率についてはそこまでの差はみられません。
しかし、1級土木施工技士の試験では、土木工事に関する幅広い知識・技術が問われます。
反対に、1級建設機械施工技士試験では、特定の建設機械に絞った専門知識と技術を求められ、土木施工管理技士のように広範囲な知識は要求されません。
したがって、1級土木施工管理技士の試験は、1級建設機械施工技士試験よりも対策が難しい試験といえるでしょう。
測量士と比較
土地の位置・面積・距離などをはかる測量士と比べると、1級土木施工管理技士試験は難易度が低いといえます。
測量士試験は、最新の測量技術や地理情報システムの知識などが問われ、また、実務経験と計画能力も必要です。
測量士の合格率は10.3%で、合格率だけでも非常に難易度が高いのがわかります。
以上のことから、1級土木施工管理士試験は、測量士に比べると難易度は低いものと位置づけられます。
- 大手求人サイトで全国トップクラスに輝いたアドバイザーが在籍
- 年収1000万円以上になった方も
- 年収350万円以上の大幅UP事例もあり
- 業界特化で「分かっている」提案。企業知識が段違い
- 休日や夜間でも専属アドバイザーが対応
令和6年から1級土木施工管理技士試験の受検資格が変更

令和6年度から、建設業法に基づく施工管理技術検定(第1次・2次検定)の受検資格の見直しが実施されます。
以前は一次試験を受けるために、最低3年の実務経験が求められていました。
しかし令和6年度からは、19歳以上なら誰でも受検できるように変更されました。
さらに、二次試験の受検資格取得に必要な実務経験期間も短縮され、最短21歳で1級施工管理技士の資格取得が可能になりました。
以下に、変更前と変更後の受検資格の一覧を掲載します。
あなたが受検資格に該当するか、確認してください。
| 変更前の受検資格 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | 第1次検定 | 第2次検定 |
| 大学(指定学科) | 卒業後3年の実務が必要 | |
| 短大、高専(指定学科) | 卒業後5年の実務が必要 | |
| 高等学校(指定学科) | 卒業後10年の実務が必要 | |
| 大学 | 卒業後4.5年の実務が必要 | |
| 短期大学、高等専門学校 | 卒業後7.5年の実務が必要 | |
| 高等学校 | 卒業後11.5年の実務が必要 | |
| 2級合格者 | 条件なし | 2級合格後5年の実務が必要 |
| 上記以外 | 15年の実務が必要 | |
| 変更後の受検資格 | |
|---|---|
| 第1次検定 | 第2次検定 |
| 19歳以上 (受検年度末時点) |
第1次検定合格後
|
1級土木施工管理技士試験の受検資格

1級土木施工管理技士は、2級よりも上位の資格として位置づけられています。
2級と同じく、受検には特定の受検資格が必要で、誰でも受検可能なわけではありません。
ここでは、令和5年度の1級土木施工管理技士の受検資格について詳しく説明します。
第1次・第2次検定の2つを受検
第1次検定と第2次検定を同時に受検する場合の受検資格を、以下の表にまとめています。
| 学歴 | 学歴と資格 | 実務経験年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
|
卒業後3年以上の実務経験年数 | 卒業後4年6か月以上の実務経験年数 | ||
|
卒業後5年以上の実務経験 | 卒業後7年6か月以上の実務経験 | ||
|
卒業後10年以上の実務経験 卒業後11年6か月以上の実務経験 |
|||
|
15年以上の実務経験年数 | |||
| 2級土木施工管理技術検定合格者 | 2級合格後 | 3年以上 | ||
| 合格後3年未満 |
|
- | 卒業後7年以上 | |
|
卒業後7年以上 | 卒業後8年6か月以上 | ||
| そのほか(学歴問わず) | 12年以上 | |||
|
2級合格後 | 3年以上 | ||
|
卒業後8年以上 | |||
第2次検定のみを受検
第2次検定のみを受検する方の受検資格は、以下に掲載する表のとおりです
| 令和3年度以降の第1次検定・第2次検定を受検し、第1次検定のみ合格した者 |
|---|
|
技術士法による第2次試験のうち以下に該当する者
|
土木施工管理技士の実務経験とは

1級土木施工管理技士検定において実務経験として認められるものは、以下の表に掲載された工事に関するものです。
| 建設工事の種類 | 工事内容 | 従事内容 |
|---|---|---|
|
|
|
土木工事に関わらない業務は実務経験として扱われないため、注意が必要です。
具体的には、以下にあげる業務は、1級土木施工管理技士試験にかかる実務経験とはみなされません。
- ⼯事着⼯以前における設計者としての基本設計・実施設計のみの業務
- 測量・調査(点検含む)・設計(積算を含む)・保守/維持・メンテナンス等の業務 ※ただし、施⼯中の⼯事測量は認める 現場事務、営業等の業務
- 官公庁における⾏政及び⾏政指導・研究所・学校(⼤学院等)・訓練所等における研究、教育及び指導等の業務
- アルバイトによる作業員としての経験
- ⼯程管理・品質管理・安全管理等を含まない雑役務のみの業務、単純な労務作業等
- 単なる⼟の掘削・コンクリートの打設・建設機械の運転・ゴミ処理等の作業・単に塗料を塗布する作業・単に薬液を注⼊するだけの作業等
\ 誰かに聞いてほしい悩みはありませんか/
1級土木施工管理技士試験の内容
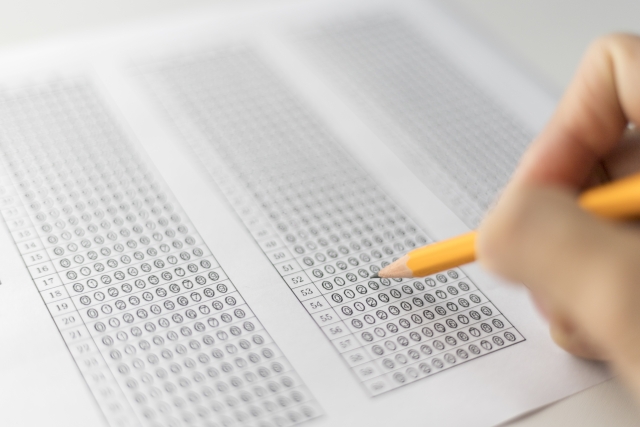
本章では、1級土木施工管理技士の試験内容を詳しく解説します。
試験は、第1次検定と第2次検定にわかれて実施されます。
試験の形式も、マークシート方式と記述式にわかれるため、それぞれの違いを把握して対策してください。
第1次検定の内容
試験形式はマークシート方式で、合格要件は全体で60%以上の得点、及び施工管理法(能力問題)でも60%以上の得点が必要です。
各問題の点数は1点で、総問題数は65問、施工管理法(能力問題)が15問です。
そのため全問題のうち39問以上、施工管理法(能力問題)のうち9問以上正解が合格基準とされています。
試験は午前と午後のセッションに分けられており、それぞれの詳細は以下のとおりです。
| 午前の部 試験時間:2時間30分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 内容 | 出題数 | 解答数 | 解答形式 |
| 土木工学等 | 土木一般 | 15問 | 12問(選択) | 4肢択一 |
| 専門土木 | 34問 | 10問(選択) | 4肢択一 | |
| 法規 | 法規 | 12問 | 8問(選択) | 4肢択一 |
| 午後の部 試験時間:2時間 | ||||
| 科目 | 内容 | 出題数 | 解答数 | 解答形式 |
| 土木工学等 | 共通工学 | 4問 | 4問(必須) | 4肢択一 |
| 施工管理法 | 施工管理法 | 16問 | 16問(必須) | 4肢択一 |
| 施工管理法(能力問題) | 15問 | 15問(必須) | 4肢択一 | |
第2次検定の内容
試験は「記述式」で行われ、合格には「得点60%以上」が必要です。
出題される問題は7問ですが、各問題の配点は明らかにされていません。
| 科目 | 出題数 | 解答数 | 解答形式 |
|---|---|---|---|
| 施工管理法 | 1問 | 1問(必須) | 記述 |
| 2問 | 2問(必須) | 記述 | |
| 4問 | 4問(選択) | 記述 | |
| 4問 | 4問(選択) | 記述 |
1級土木施工管理技士試験の申込方法
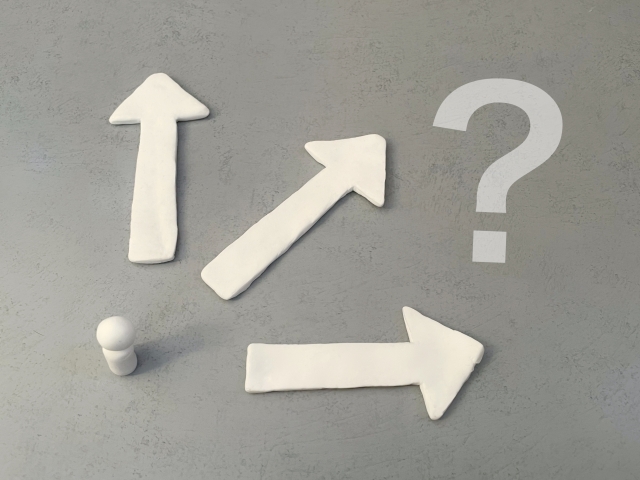
試験の申し込み方法は、申し込み者の状況により違ってきます。
以下の表を参考にして、あなたがどの方法で申し込むべきか把握してください。
| 新規受検申込者 「第1次検定・第1次検定」「第1次検定のみ」 |
初めて申込を行う方は、書面での申込が必須(受検資格の審査が必要なため) 申込用紙を購入して手続きをしてください |
| 新規受検申込者 「第1次検定のみ」 |
令和6年度から「第1次検定のみ」の申込はインターネットで行える ※住民票コード(11桁)の入力が必要(マイナンバー(12桁)とは異なる) ※住民票コードが不明な場合は、お住まいの自治体に問い合わせてください |
| 再受検申込者 | 再受検者でインターネット申込が可能な方は、検定区分によって対象者が異なる ※「インターネットでの再受検申込に際しての注意点」を確認すること |
※インターネットでの再受検申込に際しての注意点
以下の条件に該当する方は、「第1次検定・第2次検定」の再受検申込をインターネットで行ってください。
申込時には過去の受検年度と受検番号が必要なため、受検票や不合格通知等で事前に確認してください。
- 平成27年度から令和2年度までの「学科試験」に受検した者(欠席者含む)
- 令和3年度以降の「第1次検定・第2次検定」に受検した者(欠席者含む)
なお、平成16年度から平成26年度までの受検者で再受検を希望する方は、書面での申込が必要となります。
効果的な試験対策方法で合格を目指そう
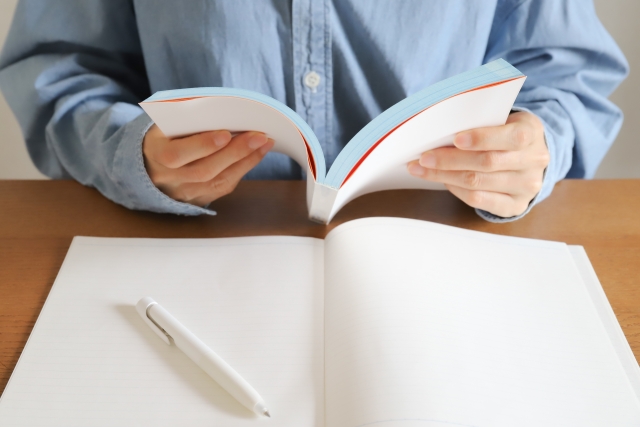
1級土木施工管理士の試験は、1次がマークシート方式で2次が記述式と、それぞれ試験方式が異なります。
また、出題される範囲も広範囲にわたるため、計画的な試験対策が必要でしょう。
ここでは合格に向けて試験勉強を進めていく際のポイントを紹介します。
試験勉強のスケジュール作成や、最後までモチベーションを切らさずにやりきるための参考にしてください。
試験勉強の計画を立てる
勉強を始める前に、まず試験までの学習計画を立ててください。
計画は長期的なものではなく、1日単位でスケジュールを作成した方がいいでしょう。
まずは、平日と休日で、具体的にいつどれだけの時間を勉強に割り当てるか計画を立ててください。
重要なのは「最大時間を目安にしないこと」です。
たとえば「1日3時間勉強する」と計画を立てると、時間が取れない日はスケジュールが狂ってしまいます。
より現実的に「平日は21時までには帰宅できるので、少なくとも1時間は勉強できる」といった計画を立てると、実行可能なスケジュールが組みやすくなります。
講習会・通信講座を受講する
「試験までやる気が続くか心配」「第2次検定の記述問題の解答が正しいか不安」と心配な方には、資格学校の講習や通信講座が役立ちます。
講習や講座では専門家の解説や、記述問題に対する添削などのサポートを受けられます。
講習や講座は、数日間の短期コースから数か月に及ぶ長期コースまでさまざまなものがあるため、自分の予算や時間に応じて最適なものを選びましょう。
1級土木施工管理技士はキャリアアップの近道
1級土木施工管理技士試験の合格率は1次検定が55.9%、2次検定が34.9%となっています。誰でも合格できる試験ではありませんが、試験の内容はそこまで難しくありません。
そのため、土木建築関連資格の中では、比較的取りやすい資格といえます。
とはいえ、受検するためには長い実地経験を必要とするため、受検するまでが大変と感じるかもしれません。
そのため、実地経験を積み上げている間に、1級土木管理技士試験の準備をしておくのが良いでしょう。
1級土木管理技士の資格を取れば仕事の幅が増え、キャリアアップや年収アップが期待できます。
ぜひ資格取得について、前向きに検討してください。
有料職業紹介(許可番号:13-ユ-316606)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社ゼネラルリンクキャリアが運営しています。








