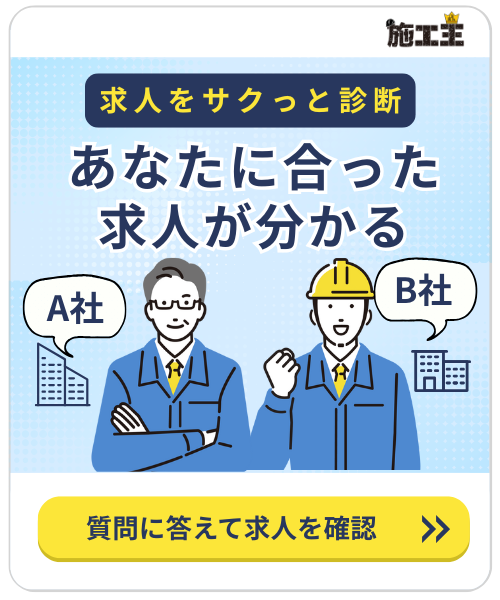目次
生コンクリート、いわゆる「生コン」は、現代の建築・土木工事においては欠かせない資材の一つで、強度や価格面の手頃さから多くの現場で用いられています。
今回はこの生コンについて網羅的に解説するので、建築・土木業界に興味がある人は本記事を今後の資料の一つとしてお役立てください。
\年収アップ、土日休みの市場にない非公開求人/
生コンとは

生コンは以下の資材を混ぜたものを指します。
- セメント
- 砂
- 水
- 砂利など
日本産業規格(JIS)では「JIS A 5308」「レディーミクストコンクリート」と称され、現在流通される生コンの多くがこの「JIS A 5308」に基づき製造・取引されています。
JIS認定を受けた生コン工場では、JISが規定する製造設備や検査設備による製造・検査が行われるなど、全てのプロセスがJISの規定により厳しく管理・流通されています。
参考:日本規格協会(JSA)|JISってなに?WHAT'S THE JIS
参考:日本産業規格の簡易閲覧|JISA0203:2019 コンクリート用語
種類・品質
JISではレディーミクストコンクリートについて4つに大別し、それぞれで管理しています。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 普通コンクリート | 呼び強度18~45(N/mm2)までのもの |
| 高強度コンクリート | 普通コンクリートよりも強度のあるもの(呼び強度60(N/mm2)まで) |
| 軽量コンクリート | 骨剤の全部、または一部に人工軽量骨材を使用し、普通コンクリートよりも軽量化したもの |
| 軽量コンクリート | 骨材の全部または一部に人工軽量骨材を使用し、普通コンクリートよりも軽量化したもの |
参考:公益社団法人日本コンクリート工学会|生コンクリートのJIS(日本工業規格)について
なお品質にもJIS規定があるので、詳細を知りたい人は「日本産業規格の簡易閲覧」内の「JISA5308:2019 レディーミクストコンクリート」よりご確認ください。
参考:日本産業規格の簡易閲覧|JISA5308:2019 レディーミクストコンクリート

誕生の歴史
現在では主流となった生コンですが、日本が最初に使用したのは、1948年12月に「東京コンクリート(株)」が設立されたことが始まりと言われています。
しかしもとを辿ると、1923年の関東大震災直後に生コンが現場に運搬・使用されたことがルーツとも言われており、いくつかの説があると考えられています。
なお、世界で初めて生コンが使われたのは1903年のドイツの建設業者と言われています。
価格は使用する材料の単位量で決められている
生コンの価格は、基準容積を1立方メートルと定め、基準容積あたりに使用する材料の配合(単位量)に基づいて算出されます。
また価格は「基準価格」を設定し、基準と異なる際に発生したコスト差を基準価格に増減する方法が取られています。
なお、日本各地の生コンの需要に違いがあるため、基準価格は各地域で異なるといった特徴があります。
コンクリートの特徴

日本は世界各国の中でも有数のセメント生産国です。
そのためコンクリートやセメントを使う機会が増加していることをご存じでしょうか。
コンクリートは水を混ぜ合わせることで固まりますが、凝固するのは化学変化によるものです。
さらにコンクリートはいくつかの種類に分かれており、24時間で凝固するものもあれば、それよりも短い時間で凝固するもの、24時間以上必要なものもあります。
セメント・モルタルとの違い
コンクリートと混同されやすい資材として、セメントやモルタルがあります。
セメントは、コンクリートの原料の一つで、石灰石などを焼成し細かく粉砕後、粉状にしたものです。
つまりコンクリートは、セメントに砂・砂利・水等を混ぜ合わせて固めたもの、これらを混ぜ合わせてドロドロになったものが生コンです。
一方モルタルは、セメントや石灰に砂を入れて水で練って生成されたもの。
コンクリートと比較すると強度は劣りますが、ブロックやレンガを積み重ねる際の目地に用いられるほか、コンクリート表面の仕上げ材として使用されます。
\年収アップ、土日休みの市場にない非公開求人/
生コンを使うメリット

世界ではもちろん日本でも多く使用される生コンですが、使用においてはどのようなメリットがあるのでしょうか。
品質維持
生コンは、工場に設置されたJIS認定を受けた設備での、配合・練り合わせにより、安定した品質を保った状態で使用できるといったメリットがあります。
コンクリートだと、資材の分量をきちんと守るだけでなく、混ぜる速度や力加減も品質に影響します。
もし仮に、分量・速度・力加減のいずれかが異なってしまうと、コンクリートの品質が低下する可能性があります。
コンクリートとの比較によってわかるように、生コンはいつでも安定した品質を保った状態で施工できる点に大きな需要があると考えられるでしょう。
作業軽減
コンクリートを工事現場で造る場合、箱形の容器やスコップなど、後に紹介するいくつかの道具・資材が必要です。
さらに、道具・資材を運ぶ人、生成するための人員の確保も必要となり、これらは工事の進捗に影響する可能性があります。
一方、生コンはミキサー車で運搬され、安定した品質の状態で使用できるので、作業軽減につながるといったメリットもあります。
人件費削減
コンクリートの配合・生成には一定数の人員確保や、資材ごとの配分について熟知した人が必要になり、その分だけ人件費がかかることになります。
しかし、生コンの使用によってこれらはカットできるので、人件費削減にも期待できるメリットもあります。
生コンの原材料

ここでは生コンの原材料を紹介します。
建築・土木業界への転職を検討される人はぜひ参考にしてください。
セメント
生コンの生成にはセメントが欠かせません。
セメントは生コンの結合材として配合され、水や溶液が混ざり時間の経過によって強度を高め、硬化が始まる特徴があります。
なお気硬性と水硬性の2つあり、生コンに用いられるのは水硬性なので購入の際は注意しましょう。
混和剤
次に混和剤を用意しましょう。
混和剤は、配合する水分量やセメントの量を減らすことができる資材です。
水やセメントの配合量を減らすことができれば工事コストの削減につながります。
さらに、セメントの硬化や乾燥の時間を短縮できるほか、水密性や強度向上、耐久性の向上にも期待できる特徴もあります。
砂・砂利
生コンの品質を決める資材として砂や砂利も必要不可欠です。
粒度によって種類が異なり、粒径5mm以上は「粗骨材」、5mm以下だと「細骨材」のように区別されています。
細かな目地には細骨材を、ブロックを積み重ねる際は「粗骨材」など、用途に合わせて適切なものを選びましょう。
生コンを造るときの道具
生コンを造るときに必要な道具は下表のとおりです。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 左官用練り舟または箱形の容器 |
|
| 練り混ぜ用のスコップ |
|
| 深型の工事用一輪車 |
|
| 20L程度のバケツ |
|
| 左官コテ |
|
建築・土木工事で使用する際は、事業所によって道具に違いがある場合も少なくありません。
自分で用意する際は、事業所の上司等に確認してから購入することをおすすめします。
生コンの概要やメリットに理解を深めよう
生コンは、コンクリートが固まる状態のドロドロとしたものを指します。
生コンの使用によって安定した品質を保つことができ、さらに生コンを生成する人件費の作成等にも役立つことから、さまざまな建築・土木工事に用いられています。
建設業界に興味がある人は、本記事を通じて、生コンの概要に理解を深めてはいかがでしょうか。
有料職業紹介(許可番号:13-ユ-316606)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社ゼネラルリンクキャリアが運営しています。